家計簿が続かない人必見!給与明細×家計簿アプリでつくる簡単マネープラン術
masayukicraft8
LIfeCraft 8+
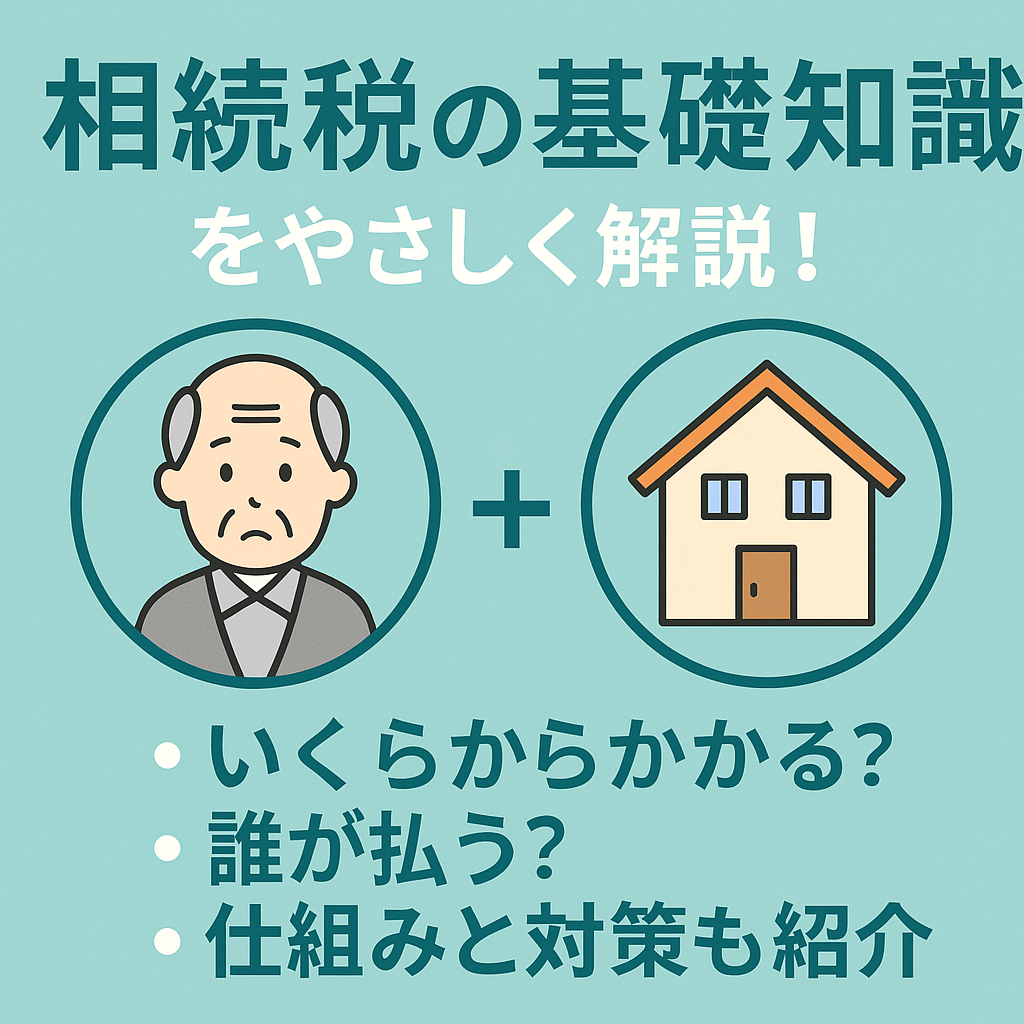
「相続税っていくらからかかるの?」「誰が払うの?」「仕組みが難しくてよくわからない…」そんな不安をお持ちの方に向けて、相続税の基礎知識をわかりやすく解説します。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得したときにかかる税金です。
相続税の対象となる財産は、以下のようなものが含まれます。
相続税を支払うのは、財産を取得した相続人(配偶者や子どもなど)です。
相続税の申告と納付の期限は、相続開始(通常は死亡日)から10か月以内と定められています。
納税は基本的に「現金一括払い」ですが、場合によっては分割して支払う「延納」や、不動産などで納める「物納」も認められています。
実は、すべての人に相続税がかかるわけではありません。相続税には基礎控除があり、これを超える場合にのみ課税されます。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人であれば、基礎控除額は4,200万円になります。この金額以内の相続財産であれば、相続税はかかりません。
相続税は以下のような流れで計算されます。
税率は取得金額に応じて10%~55%と累進的に設定されています。
生前からの対策で相続税の負担を軽くすることも可能です。代表的な節税対策をいくつかご紹介します。
「相続はまだ先の話」と思っていても、突然のこともありえます。相続税の納税資金が準備できず、不動産を手放すケースも少なくありません。
専門家(税理士や司法書士など)に相談することで、円満で節税効果の高い相続の実現が期待できます。
まずは「自分や家族に相続税がかかるのか?」を知ることから始めてみましょう。