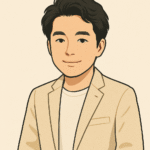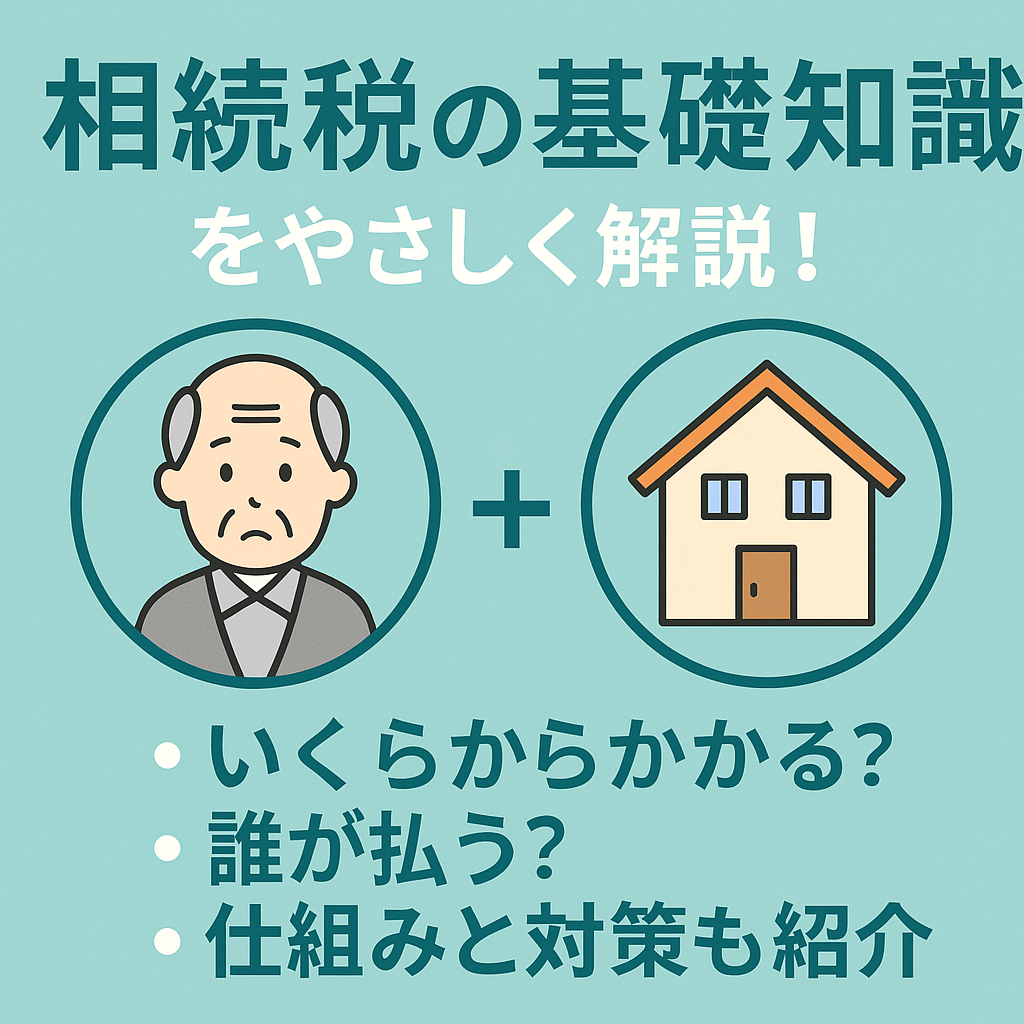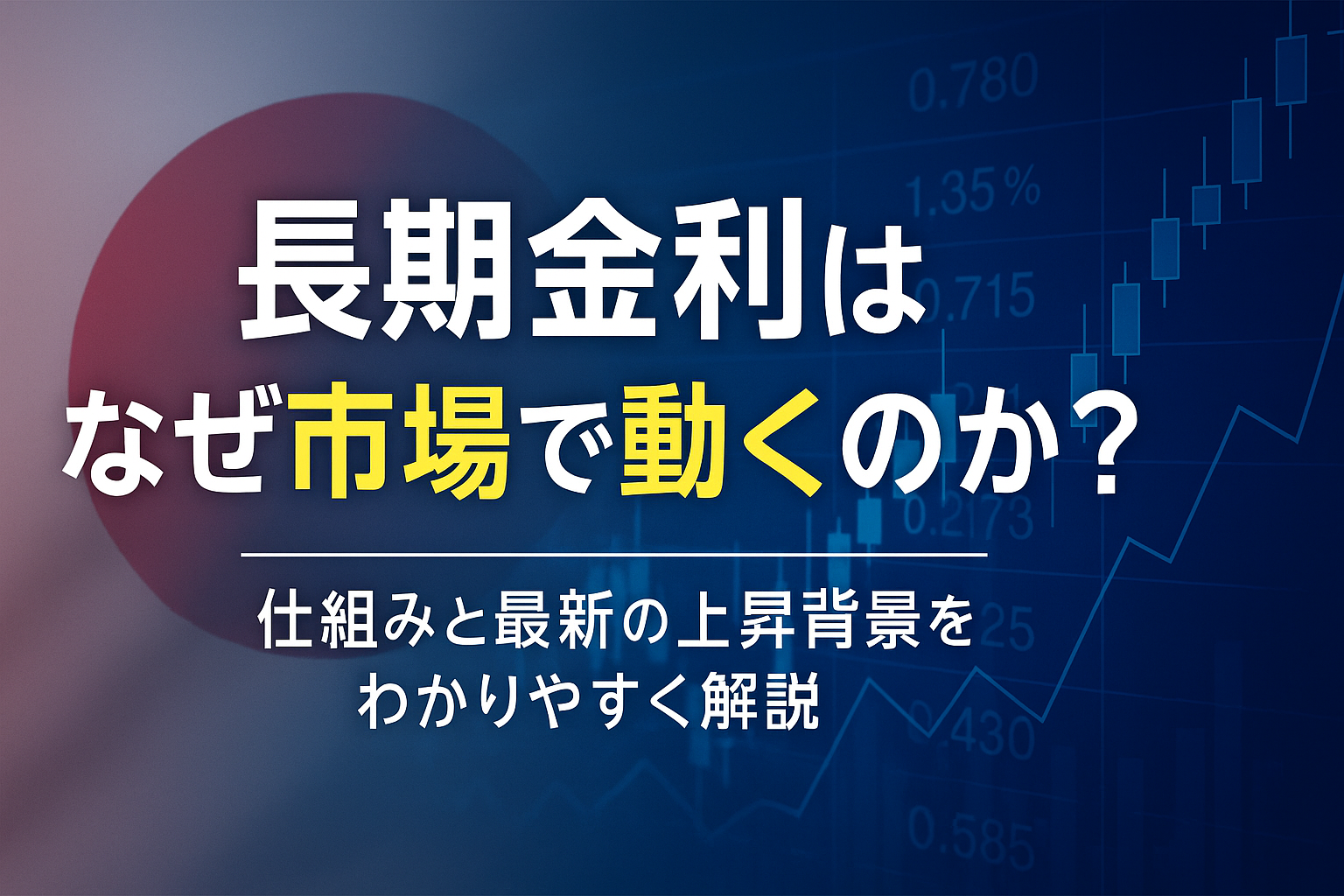相続放棄の手続きと期限|知らないと損する注意点とは?
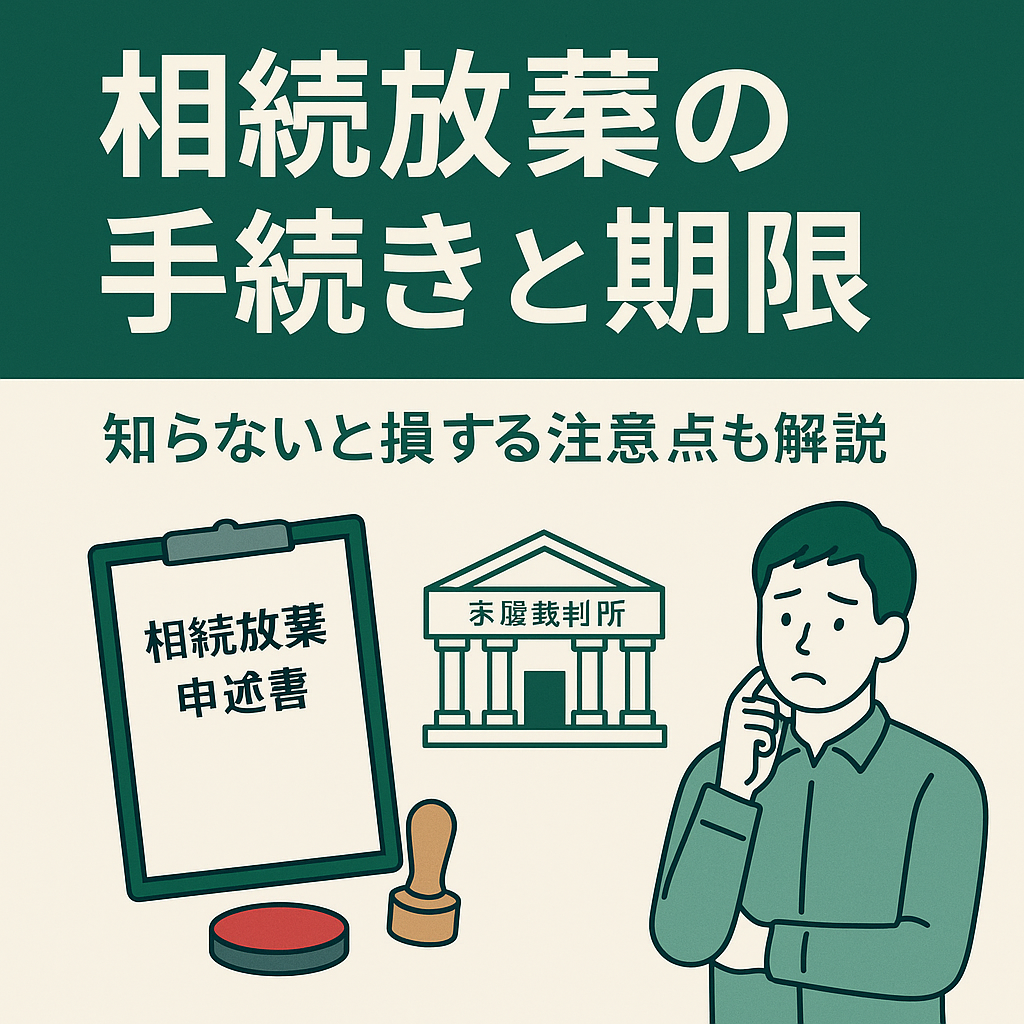
「親の借金を相続したくない」「突然、知らない親戚の相続人になっていた…」
こんなときに知っておきたいのが相続放棄という制度です。
相続放棄をうまく活用すれば、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。
しかし、期限やルールを知らないと、放棄できなくなるリスクも。
この記事では、相続放棄の基本から手続き方法、気をつけたいポイントまでをやさしく解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての立場を最初からなかったことにする制度です。
通常、相続が発生すると「プラスの財産(預貯金・不動産など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・ローンなど)」も相続の対象になります。
相続放棄をすることで、一切の財産を相続しないことができるのです。
たとえば──
・多額の借金を抱えた親が亡くなった
・相続しても利益よりリスクの方が大きい
こうした場合、相続放棄は有効な選択肢となります。
2. 相続放棄できる期間は「3か月以内」!
相続放棄には明確な期限があります。
原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」に手続きをする必要があります。
これを「熟慮期間」と呼びます。
▽こんな場合に注意!
- 遠方に住む親族が亡くなったことを後から知った
- 遺品整理の途中で借金の督促状が届いた
こうしたケースでは、「相続を知った日」から3か月がカウント開始になります。
状況によっては熟慮期間の起算日を調整できるケースもあるので、すぐに家庭裁判所や専門家に相談しましょう。
3. 相続放棄の手続き方法
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することで行います。市役所や法務局では受け付けていません。
(1)必要書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページで入手可能)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 申述人の戸籍
- その他、住民票や郵便切手など
(2)提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(3)費用・所要時間
- 収入印紙:800円
- 郵便切手代:数百円〜1,000円程度
- 審査期間:1〜2か月ほど(状況による)
4. 注意すべき3つのポイント
(1)一度放棄すると撤回できない
相続放棄は原則としてやり直しがききません。
「やっぱり財産があるなら欲しい」…と後から思っても、受け取れません。
(2)財産を一部使ってしまうと放棄できない
例えば、相続財産から葬儀費用を支払ったり、預金を引き出して形見分けしたりすると、「相続を承認した」と見なされ、放棄ができなくなる可能性があります。
(3)他の相続人に迷惑がかかることも
自分が放棄すると、次の順位の相続人(兄弟や甥姪)が相続することになります。
事前に他の相続人と話し合っておくと、トラブルを避けられます。
5. 相続放棄すべきか?判断のポイント
相続放棄を検討する際は、以下の点を確認しましょう。
- 借金の有無と金額(信用情報や金融機関に確認)
- 財産の種類と価値(不動産、預貯金、負債など)
- 他の相続人の考え(連携して対応すべき)
相続の内容が複雑な場合や、判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
相続放棄は、マイナスの財産から自分を守る大切な制度です。
しかし、期限や手続きを誤ると、放棄できずに借金を背負うリスクもあります。
- 相続開始を知った日から3か月以内に手続きを
- 家庭裁判所への申請が必要
- 一部でも財産を使うと放棄不可になることも
相続に不安を感じたら、できるだけ早く専門家に相談しましょう。